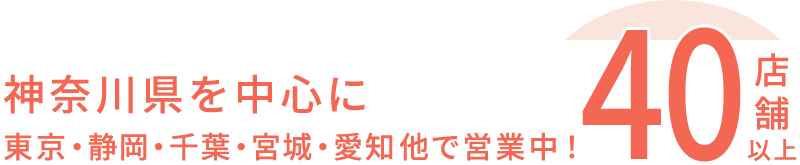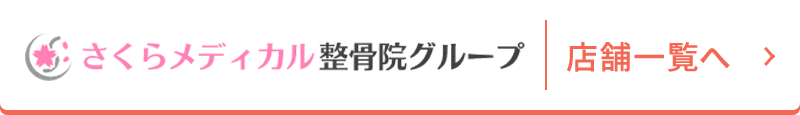胸郭出口症候群の
基礎知識
胸郭出口症候群の症状
胸郭出口症候群は、首と胸の間を通る神経や圧迫が起こることで生じます。
神経症状
-
肩から腕を通る神経が圧迫されるため肩や腕、手に神経症状が現れます。痛みやしびれ、だるさなどを覚えるでしょう。
また、運動神経が圧迫されることで握力の低下、手指の運動障害などが生じることもあります。
手や腕の血行不良
-
鎖骨下動脈、静脈が圧迫を受けることで、手や腕の血行が悪くなります。手や腕の血行が悪くなると冷えが生じ、皮膚が白っぽくみえることがあります。また、老廃物が排出されにくくなることでむくみも生じやすくなります。
胸郭出口症候群の原因
胸郭出口症候群には、次の3つのタイプがあります。それぞれの発症原因は次のとおりです。
-
首から肋骨にかけて存在する前、中斜角筋の間のトンネルが狭くなることで生じます。
首に負担がかかり、斜角筋が緊張して生じることが多いです。不良姿勢やいかり肩などの体型が原因として挙げられます。
斜角筋症候群
-
鎖骨が下がって肋骨の間が狭まってしまうことが原因として挙げられます。猫背姿勢やなで肩が原因で起こります。
鎖骨を骨折し、きちんとリハビリを行わなかった場合にも起こります。
肋鎖症候群
-
小胸筋が緊張することで血管や神経を圧迫している状態です。不良姿勢やなで肩などが原因で生じます。
小胸筋症候群(過外転症候群)
胸郭出口症候群の症状
胸郭出口症候群は、首と胸の間を通る神経や圧迫が起こることで生じます。
-
肩から腕を通る神経が圧迫されるため肩や腕、手に神経症状が現れます。痛みやしびれ、だるさなどを覚えるでしょう。
また、運動神経が圧迫されることで握力の低下、手指の運動障害などが生じることもあります。
神経症状
-
鎖骨下動脈、静脈が圧迫を受けることで、手や腕の血行が悪くなります。
手や腕の血行が悪くなると冷えが生じ、皮膚が白っぽくみえることがあります。
また、老廃物が排出されにくくなることでむくみも生じやすくなります。
手や腕の血行不良
胸郭出口症候群を
発症した際の注意点
胸郭出口症候群は手や腕に症状が現れるため、日常生活に影響を与えることも少なくありません。
適切な対処で症状の緩和や早期回復を目指しましょう。
-
首の筋肉が緊張して硬くなると、血管や神経を圧迫して胸郭出口症候群を引き起こします。
緊張した筋肉は温めることでほぐれるため、首まわりの筋肉を温めるようにしましょう。
カイロで部分的に温める、入浴で全身を温めることも大切です。
首まわりの筋肉を温める
-
猫背姿勢など日常的に姿勢が悪いと、部分的な負荷が加わることで胸郭出口症候群を引き起こします。
症状の緩和や予防のためにも、日頃から姿勢を正すことを心がけてください。
とくにデスクワークなど長時間同じ姿勢が続くときには姿勢が崩れてしまったり、筋肉がこり固まったりするため注意が必要です。
姿勢を矯正する
-
硬くなった筋肉の柔軟性を取り戻せば、筋肉の圧迫がゆるんで症状の緩和や改善が期待できます。
セルフマッサージやストレッチを日頃から行うようにしましょう。
首を回す運動だけではなく、肩や肩甲骨も動かすことも意識してください。
セルフマッサージや
ストレッチを行う
胸郭出口症候群に
ならないための予防法
胸郭出口症候群は日常から予防やケアを心がけることで予防できます。
-
肩にある僧帽筋を鍛えることは、首や肩にかかる負担の軽減につながります。
首や肩に筋緊張が起こることを防いで胸郭出口症候群の発症リスクを下げられます。
僧帽筋を簡単に鍛える方法として、水の入ったペットボトルなどをダンベルに見立てて運動を行います。
肘を曲げずに顎の高さまで持ち上げて下ろすことを繰り返してみましょう。
僧帽筋を強化する
-
肩にかかる負担が蓄積されると筋緊張から胸郭出口症候群が起こりやすくなります。
日頃からに負担をかけないように注意しましょう。
片側の肩ばかりにバッグを掛ける、長時間の同一姿勢や猫背姿勢は肩に負担がかかります。
こうした日常の習慣を見直すことが予防の第一歩です。
肩の負担を減らす
-
腕を挙げる動作は、神経や血管が圧迫されやすくなります。
胸郭出口症候群の疑いがあるときには、腕を挙げる動作を控えるようにしましょう。